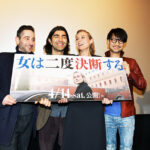映画が完成した後、私はすばらしい旅を終えたような気がした
偉大なる作曲家ベートーヴェンの晩年に焦点を当て、狂気のごとき創作活動とその苦悩、写譜を務めた若き女性作曲家との深い絆を描いた『敬愛なるベートーヴェン』。ハリウッドでも活躍するポーランドの女性監督アニエスカ・ホランドが、ベートーヴェンへの“敬愛”をこめて、ベートーヴェンの音楽のすばらしさを再発見させる本作について語ってくれた。
アニエスカ・ホランド監督
1948年11月28日、ポーランドのワルシャワ生まれ。
プラハのFAMUで映画と演出を学んだのち、ポーランドに戻り、クシシュトフ・ザヌーシ監督の助監督として映画界に入る。『Aktorzy prowincjonalni』(79)で、カンヌ国際映画祭の国際映画批評家連盟賞を受賞。ベルリン国際映画祭に出品され、主演女優賞を受賞した『Goraczka』(81)でさらに国際的な注目を集め、『Bittere Ernte』(86)でアカデミー外国語映画賞にノミネート。
エド・ハリスが出演した『ワルシャワの悲劇/神父暗殺』(88)を経て、『僕を愛したふたつの国/ヨーロッパ ヨーロッパ』(90)で米アカデミー賞®の脚色賞にノミネートされたことから、海外での名声を不動のものにした。『
秘密の花園』(93)でハリウッドに進出したのち、レオナルド・ディカプリオとデヴィッド・シューリスを主演に、詩人ランボーとヴェルレーヌの禁断の関係を描く問題作『太陽と月に背いて』(95)を発表し、高い芸術性を絶賛された。
以前からエド・ハリスさんとは何度かお仕事をされていますが、今回再び彼を起用した理由をお聞かせください。
エド・ハリスという俳優は、とても深く複雑な人なの。だから、ベートーヴェンという偉大で複雑な魂の持ち主を演じるだけの技術のみならず、精神力があるし、役に対する好奇心と責任感もある。だから、彼がピッタリだと思ったの。この役を演じるためには肉体改造が必要だったし、徹底的に音楽を勉強しつつ、天才の内面を表現しなければならないという、非常にハードルの高い課題があった。これをクリアできる俳優はそうはいないわ。でも、エドなら出来ると私には分かっていた。随分以前からお互いのことを知っているし、あえてリスクをも冒せる信頼関係にあるから。彼を起用して本当によかったと思うわ。
ベートーヴェンの晩年とアンナ・ホルツという女性の存在を描いていますが、なぜ晩年に焦点を当てたのですか?
アンナ・ホルツという女性は架空の人物だけど、全くあり得なかった存在ではなく、その当時、ベートーヴェンの周囲に実際にいた人間たちのさまざまな要素を取り集めて、存在していたであろう作曲家志望の才能ある若い女性というキャラクターを作り上げたの。彼女の純粋な目を通して私たちが、ベートーヴェンのパーソナルな部分を見ることができると思った。
なぜ晩年を選んだかというともちろん、この時期に偉大な音楽がたくさん生み出されたからよ。そして、音楽はどんどん偉大になっていくのに、ベートーヴェンの健康状態や彼を取り巻く環境はどん底に向かっていた。そこに興味を惹かれたの。

アンナ・ホルツ役も重要でしたが、ダイアン・クルーガーを起用した理由をお聞かせください。
実は、ダイアンがこのキャラクターを演じるにふさわしいのか、エド・ハリスのような偉大な俳優と対等に渡り合えるだけの才能があるのか、私には確信がなかった。でも彼女は、自分こそアンナ・ホルツだと信じていて、「それを証明してみせる」と言ったの。それで、当時私はロスで別の作品を撮影していたんだけど、彼女はニューヨークから夜中に私の家にやって来たわ。エドにも来てもらい、私の娘がカメラを回して、うちの暖炉の前で二人にあるシーンを5分間演じてもらったところ、彼女のすばらしさがはっきりと分かったの。とても誠実で力強い演技だけど、はかなげで繊細なところがあるのもよかった。エドに向かって話しているときも、気後れしながらおずおずとではなく、堂々として確信に満ちていた。実は、彼女に会ったときはまだ『トロイ』などが公開されていなくて見ていなかったんだけど、見ていなくてよかったと思う(笑)。それらの映画の中では、彼女はもちろん美しいけれど、豊かな演技を披露しているとは言えなかった。でも、この映画で一緒に仕事をして、彼女の才能と誠実さを知ることができたわ。
今作では“第九”のシーンが最大の見せ場でしたが、それと同じくらい印象的だったのが、“大フーガ”をはじめとする晩年の弦楽四重奏曲でした。これらを聴くと、ベートーヴェンは時代が追いつけないくらい先を進んでいた作曲家だったと実感しましたが、監督はどう思われますか?
私は、ベートーヴェンという人は生まれるべくしてあの時代に生まれたと思っているわ。“大フーガ”というのは本当に難しくて、当時の人たちは「あんな曲を書くなんて、彼は狂ってしまったか、よほど耳が悪いに違いない」と言っていたくらいなの。この“大フーガ”は弦楽四重奏曲第13番の終楽章として作曲されたんだけど、「こんな変な終楽章がある曲は売れない」と言われたベートーヴェンは結局、この部分を切り離さざるを得なくなったのね。それで70年ほどの間、見向きもされなかったんだけど、後の偉大な作曲家たち、メンデルスゾーンやブラームス、ワグナーがこの曲を愛したの。だから、ベートーヴェンは、後の作曲家たちにインスピレーションを与えたわけで、もしかしたら彼なくしては、そうした音楽家たちも生まれなかったかもしれないと思うわ。
面白いことに、ベートーヴェンの苦労は今の私の苦労と同じなの。編集者とぶつかり、妥協せざるを得なくなる。「この作品はあまりに風変わりだし長すぎるから、カットしましょう。そうしたらもっと高く売れますよ」と言われるわけよ(笑)。
何年たっても人間はあまり変わらないということね(笑)。

今回は選曲に苦労されたのでは?
私は“大フーガ”が大好きなので、どうしてもこの映画で使いたいという思いがあったの。ただ、あの難しい曲をいきなり入れても、観客には伝わらないと思ったので、その前に“第九”を持ってきたのよ。“第九”で観客を音楽に引き込んだところで、私が本当に聴いていただきたかった曲を入れたの。
芸術に対する深い洞察が感じられる映画でした。このようにレベルの高い作品を形にするのは、大きな困難を伴うものではないでしょうか?
私はこの映画を作ることによって、ベートーヴェンへとたどり着く旅路を経験したの。観客の方たちも同じような経験をしていただけるといいのだけど。私はそれほど音楽に詳しい人間ではないわ。もちろん、音楽は大好きだけど、それは皆さんと同じ程度よ。一方で私は、音楽は芸術の中でも最高の芸術であり、映画の最高の友だと思っている。この映画を作ることで私は、異なった視点で音楽の中に深く入り込むことができたと感じているの。映画が完成した後、私はすばらしい旅を終えたような気がした。音楽をじっくりと聴きこんだし、音楽によって自分自身を豊かにすることもできたわ。だから、私が経験したこの心の旅ともいえるものが映画に反映していて、観客も同じような印象を受けていただけるとうれしいと思うの。それができたら、この映画は成功したと言えるわ。
あまり音楽は詳しくないとおっしゃいましたが、ベートーヴェンが“第九”にこめた思いをどのようにお考えですか?
確かに、最初はあまりベートーヴェンのことを知らなかったけど、今は何でも聞いてもらっていいわ(笑)。“第九”がすばらしいのは、これまでの交響曲とは全く違った傑作であるということね。彼にとってはとても大きな意味のあったシラーの詩を使って、コーラスを入れたというのも新しいことだった。音楽と言葉によってメッセージを伝えようとしたのよ。ベートーヴェンはこれまでオペラも作曲したことはあるけど、成功したとは言えなかった。“第九”はいわば、彼にとってのオペラだったと思うの。それに、曲の構造を調べてみると、もちろんこれまでの交響曲のルールに従っているところはあるけど、全く新しい試みがある。一方で、「歓喜の歌」はとてもシンプルで、五つの音符しか使っていないのよ。先ほど、指揮者の佐渡裕さんと対談したんだけど、そのとき佐渡さんは子供が使うような小さな笛で「歓喜の歌」を吹き、五つの音符しか使っていないことを示してくれたわ。つまり、非常に複雑で濃いメッセージを、実にシンプルな形で伝えている曲なのよ。それがこの曲のキーになっていると思う。

実在した人物を描くことの難しさを感じたりされませんでしたか? どのような点に注意されたでしょうか。
私はこれまでも、歴史上の有名無名な人物を主人公にした映画を撮ってきたので、実在の人物を描くのは非常に難しいし、責任も重いことは分かっている。それに、ベートーヴェンのような有名な人物は特に、皆さんそれぞれ、自分なりのイメージや意見を持っているわね。でも、そういうことは考えないようにして、自分の見方が正しいと思って映画を作るしかないわ。結局、どのような描き方をしても、批評家たちは「ここは違っている」と言うに決まっているのよ(笑)。そう言われたら、「あなたたちに何が分かるの? 私はもっと知っているわ!」と言い返すけどね(笑)。
監督はショパンが生まれたポーランドのご出身で、クラシック音楽とは密接な関係にあるお国柄だと思いますが、実際のところはいかがでしょうか?
ポーランドというのはとてもおかしな国なの。偉大な作曲家が何人も生まれているのに、国民は歌が下手で音痴が多い。集まって歌い出すとみんな、音がはずれているのよ(笑)。音楽祭をやってもあまり盛り上がらないし。今はたぶん、日本の方がクラシック音楽は愛好されていると思うわ。ショパン・コンクールなどで優勝するのはいつも、日本人か中国人、韓国人ばかりじゃない? だから、ヨーロッパはもちろん、クラシック音楽が生まれた場所としての誇りと伝統はあるけれど、現在も息づいているかというと疑問で、もしかしたらアジア、特に日本の方が良い土壌になっているんじゃないかしら。そんなわけで、私はこの映画の最良の観客は日本人だと思っているんだけど(笑)。
ショパンはポーランド人で、私も小さい頃から彼の音楽を日常的に聴いてきたことは間違いないわ。例えば、誰かが亡くなったとか何か大きな事件が起こると必ず、ラジオからショパンが流れていたわね。ただ私にとっては、ベートーヴェンが最初のクラシック音楽との出合いだったの。その後、モーツァルトやバッハが来て、ショパンは四番目くらいだったかもしれない。ショパンの深さが分かってくるのはやはり、大人になってからじゃないかと思う。今は私もショパンは好きよ。
ショパンについては過去、5~7本の映画が作られているけど、彼を描くのはまた、ベートーヴェンとは違った意味で難しさがあると思うわ。


数々の名作をものにされてきたホランド監督だが、その素顔はとっても陽気でお茶目。終始楽しげに答えてくださり、インタビューが終了すると、一体どこで覚えてきたのか、「ありがと~ありがと~♪」と日本語で歌い出したり。
とにかくこの映画、師弟の美しいコラボレーションが実現する“第九”のシーンも見どころながら、監督がどれよりもお好きだという“大フーガ”の古典を超えたユニークさには圧倒され、心底驚かされる。ぜひ、この映画でベートーヴェンを発見していただきたい。
(文・写真:Maori Matsuura)
『敬愛なるベートーヴェン』作品紹介
1824年ウィーン。“第九”の初演を4日後に控えたベートーヴェンのアトリエに、作曲家を志す若き女性アンナがコピスト(写譜師:作曲家が書いた楽譜を清書する職業)として訪れた。期待に反し、女性のコピストが来たことに激怒するベートーヴェンだったが、徐々に彼女の才能を認め、“第九”の作曲を支える存在となる。昼夜を問わない創作活動を通して、二人の間には師弟愛以上の感情が芽生えていく。そして、ついに“第九”初演の日、耳の聞こえぬ恐怖を抱えながらも、オーケストラを指揮するために、ベートーヴェンはケルントナートーア劇場の舞台に立つのだった……。
(2006年、イギリス=ハンガリー、104分)
キャスト&スタッフ
監督:アニエスカ・ホランド
出演:エド・ハリス、ダイアン・クルーガー、マシュー・グッド、フィリーダ・ロウほか
公開表記
配給:東北新社
2006年12月9日(土)より日比谷シャンテシネ、新宿武蔵野館、シアターN渋谷ほか全国ロードショー
(オフィシャル素材提供)


![敬愛なるベートーベン [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51uj8WYQHAL._SL160_.jpg)

![ソハの地下水道 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51gxV5Kr1vL._SL160_.jpg)

![赤い闇 スターリンの冷たい大地で スペシャル・プライス[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51s79t+s-HL._SL160_.jpg)

![太陽と月に背いて [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51GFJZ566NL._SL160_.jpg)

![奇蹟の詩 ~サード・ミラクル~ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51J7BSFP6JL._SL160_.jpg)