
異性であろうが同性であろうが、物体であろうが、好きになってしまったら、そこからラブ・ストーリーは始まると思うんです
1988年にミニシアター「中野武蔵野ホール」で初公開されて以来、両極の反響を巻き起こしつつ、毎年のように上映されてきた伝説のカルト・ムービー『追悼のざわめき』が、この2007年、デジタルリマスター版として甦る。タブーとされてきたテーマに向き合い、猥雑で汚濁に満ちた世界の中から立ち上がる聖性と美、静謐なる哀しみを描いた松井良彦監督に、初公開から20年近く経った今もなお、おぞましくも美しい輝きを失わない本作について話を聞いた。
松井良彦監督
1956年生まれ。
ホモセクシュアルの三角関係を描いた、処女作『錆びた缶空』(1979年/撮影:石井聰亙)が、「ぴあ」誌主催のオフシアター・フィルム・フェスティヴァル(現PFF)に入賞。一部に熱狂的なファンを持つ、いわば“カルト・ムービー”の草分け的存在となる。
続く第二作は、在日韓国人の男女の愛と差別による別れを鮮烈に描いた『豚鶏心中』(81年/撮影:原 一男)。
故・寺山修司氏の天井桟敷館で長期ロードショーを果たした。第三作『追悼のざわめき』(88年)は、脚本を読んだ故・寺山修司をして「映画になったら事件だね」と言わしめ、実際の撮影も難航するが、撮影開始から4年後の1988年5月、今は無き中野武蔵野ホールにてロードショー開始。同館開設以来の観客動員記録を打ち出した。同作は、2007年、『追悼のざわめき デジタルリマスター版』として甦ることになる。
そして、長年待ち望まれていた新作『どこに行くの?』は2008年早春、ユーロスペースにて公開が決定している。
監督は現在、京都にお住まいなんですね。ご出身はどちらなんですか?
兵庫県の西宮です。甲子園球場の近所ですわ。僕は高校を卒業後、すぐ東京に来て、40歳くらいまでいたんですよ。で、38~39歳くらいの頃に阪神淡路大震災があり、まあ、諸事情で引っ越すことになって、だったら『追悼のざわめき』は毎年京都では上映していただいていましたし、知り合いも多いし映画人もいますから、京都に引っ越すことにしたんです。西宮に帰ってしまうと完全に映画から離れてしまいそうな気がして、京都に住むことにしたんです。京都に移って、もう10年目になるかな。
ウェブの日記に「本当に京都で良かった」と、京都に住む喜びを繰り返し書かれていますね。
(笑)読んでいただいた? ありがとうございます。その通りです。明日帰れるんですよ(笑)。こちら(東京)には新作(『どこに行くの?』)のこともあったので、来ていました。4月から準備が始まって、5月に京都にちょっと帰って、それからはずっとこっちにいました。公開は、来年早春になります。
主演は柏原収史さんですね?
ええ、気持ちの優しい、良い男ですよ。実を申し上げると、はじめは存在すら知らなかったんです。で、プロデューサーと話をしていて、「イメージしているキャストはいるんですか?」と聞かれたんですが、脚本を書くときにはいなかったんですね。20代半ばから30代手前くらいの人でいろいろ探したんですが見つからず、下北沢で演劇をやっている方たちにも会ったんですが、なかなかイメージに合う人がいなくて。その後、プロデューサーが出してきたリストの中で、作品歴を読んでも、彼が一番良いと思ったんですね。柳町光男監督の『カミュなんて知らない』にも出ていた人なので、この脚本も受け入れられるかなと思って渡したら、すぐに返事をくれて、その後はプライベートでも頻繁に会って、いろいろ話をするようにしました。それでますます“ええヤツやな~”と(笑)。
新作はどういった内容ですか?
少年時代に養父からホモセクシャル的な行為を受けて、それがトラウマになって育った青年とニューハーフの人が出会い、そこからドラマが始まるという……。
そのニューハーフの方というのは……?
ほんまもんのニューハーフで、新宿で一番売れている可愛い方です。今頃、彼女は試写を観てますわ。
『追悼のざわめき』、稀にみる素晴らしい作品だと心揺さぶられました。今回、デジタルリマスター版になり、16ミリ・フィルムと違いは感じられましたか?
それが、そんなにないんですね。16ミリでモノラル録音の映画をデジタルにしようかという話になったとき、最初は“違う作品になったらいいな”と思ったんですよ。でも、フィルムであろうがデジタルになろうが、そんなにガラッと変わるような映画じゃないよなと、自分でも観終わった直後に思いましたね。ただ、今回新たに上田 現君に音楽をつけてもらいまして。16ミリのほうでは別の音楽を使っていたんですが、それだと、女子高に乱入する小人症の夏子が怪物に見えたんですね。それが、上田 現君が作ってくれた曲だと、非常に悲しい、行き場のない辛い女というタッチになったと思えましたので、彼に頼んで本当に良かったです。16ミリ版のほうではやりたかったけど出来なかったことを、上田 現君がやってくれました。
猥雑で汚濁に満ちた世界から、聖なるもの、暴力的なまでの美が立ち上がってくるような作品です。どのようなところから発想されたのですか?
よく聞かれるんですが、自然に湧き上がってきたので、何とも言えないんですよね。自分でも考えると、こじつけかもしれないんですけど、『錆びた缶空』(1979)という最初の映画ではホモセクシュアルを描いたんですが、当時ホモセクシュアルは大手を振って町を歩ける時代じゃなく、テレビに出るのもピーター(池畑慎之介)や三輪明宏さんくらいで、その後に作った『豚鶏心中』(81)という映画では在日韓国人や部落の人たちを扱ったんですね。それらも自然と湧き上がってきて、“撮りたい”と思ったんです。で、『追悼のざわめき』では町自体が疎外されている釜ヶ崎で、そこで愛する対象物がマネキンであったり、自分の妹であったり、股の形をした木であったりという……。疎外されている人たちに自然と、僕は眼が向いちゃうんです。で、登場人物にとっては純粋な愛なんですけど、周りから見るといわゆる変質者なわけで、でも異性であろうが同性であろうが、物体であろうが、好きになってしまったら、そこからラブ・ストーリーは始まると思うんです。例えば、好きでもない相手が金持ちだからという理由で結婚する人より、はるかに純粋だと思いますよ。
この作品が作られたのはまさにバブル真っ只中で、一方でサブ・カルチャーが盛んだった時代でもありますね。その中にあって、監督も創ることに対する渇きみたいなものは感じていらっしゃいましたか?
それはたぶん、サイクルがあるんだと思いますよ。僕らの上の世代だと唐 十郎さんや寺山修司さん、映画では大島 渚さん、若松孝二さん、音楽ではフォークがあったり、その時代独自のムーブメントがあったりしたように、周期的にやってくる気がしますね。人間の目には見えない力が動いているのかもしれない。だから、これから数年したらまた、若い世代たちがそういう動きをつくる気がします。
僕自身は、特にそういった空気に影響されたというわけじゃないんですけど、当時“思ったことはやりたいな”とは考えていました。そこで、目に見えない力で寺山さんと会うことになりましたし、石井聰亙と一緒に「狂映舎」という映画の製作グループを作ることになったりして、そこで助監督や編集をさせてもらっている内に「松井君も1本撮ったら?」と言われて、『錆びた缶空』を撮ることになったわけです。戦略的に動いていたわけじゃなく、たまたまそういう環境に身を置けていたということがありますね。で、1本監督をやってしまうと、表現する喜びというのは非常に大きくて、またスタッフが、監督のイメージするものを撮らせてやろうと一生懸命にやってくれるんですよ。それがまた嬉しくて、古い言い方ですけど、同志というか戦友というか、そういう仲間意識がとても嬉しいな、という。本当に快感なんですよ。それがあるから、『追悼のざわめき』から年月が経とうが、やっぱり映画を撮りたいなと思い、実際に撮ってみたらやっぱり現場は楽しんです。限られた予算と日数で、これは撮れないんじゃないかと思うようなシーンでも、みんなが知恵と気持ちを傾けて工夫してくれて、何とか撮れたりするんですよね。そういうのが本当にたまらないです。
『追悼のざわめき』には寺山修司さん的な空気がありますね。
ありますね。やっぱり影響は大きかったです。中3か高1のときに『田園に死す』を観て、わけ分かんなかったんですよ。それで、「わけの分からん映画作るな」って葉書を書いて出したんです(笑)。それは夜のことだったんですけど、夜って魔物がいるでしょ? それで翌日目が覚めて“えらいことしたな”と……(笑)。修学旅行で東京に来たら、その頃渋谷に天井桟敷館があって、たまたま寺山さんと話せる機会があり、「うん、覚えてるよ」って。それからしばらく会わない期間があったんですが、『錆びた缶空』撮ったときに観ていただき、そこからたまにですけどお話しさせていただく時間があって、観客と映画監督でないところでお話が聞けたというのは、やっぱり非常に影響されていますよね。生の声で、為になる話もくだらない話も聞けたわけですから。それに、当時のATG(日本アート・シアター・ギルド)映画を支えた監督さんたちとは本当に良く会える機会ができたので、やはりそういう映画を自然と志向するようになりましたね。
その寺山さんでさえも、「この映画は難しいかも」とおっしゃったんですね?
そうですね(笑)。「難しい」というより「無理だろう」と。やはり、世の中が伏せているタブーを描いているので、仮に撮影は出来ても、その後にいろいろな障害が出るだろうし、劇場も貸さないだろうし、まず脚本読んだ段階で「出たい役者はいないだろう」と言われました。
でも、寺山さんの映画も相当タブーに触れてますよね?
(笑)でも、名前がありましたからね、寺山さんには。
でも結局、出演する方たちがいたわけですが、仲井まみ子さんはどのようにして見つけられたんですか?
『錆びた缶空』を創った当初から、小人症を扱った映画を撮りたいなと思っていたんですよ。そのときには『胎児の玩具』というタイトルで脚本を書いていて、8ミリ映画を撮ろうと思って出演者を探していたんです。京都に知り合いが多かったので、京都でいろいろな人に声をかけても「おるわけないやろ」と言われてたんですけど、何年間も言い続けていると「松井、本気だ」ということで、そのうちの一人が行っている店にたまたま小人症の彼女がいたんです。それで「出てみない?」と声をかけてもらい、はじめは「抵抗がある」と言っていたみたいなんですけど、「監督が面白い人だから、とにかく会ってみたら?」と説得してくれて、会えたわけです。そのときにはもう『追悼のざわめき』の脚本があったので、渡して読んでもらい、再び会ったときに言われたことが「わたし、いじめられるんですね?」でした(笑)。「いじめられるというのではなくて……」と説明し、仲井さんの部分以外のところは撮影に入っていたので、「現場に遊びにおいで」と誘いました。現場ではみんな一生懸命やっていますから、それを見て“面白そう”と思ってくれたみたいで、出演を承諾してくれたわけです。
いろいろと辛いシーンはあったと思いますが、仲井さんとしてはどうだったのでしょう?
「辛い」ということは、少なくとも僕の耳には入ってきませんでしたね。でも、現場はみんな楽しくやっていたんですよ。あの美少女を演じた村田友紀子さんにしろ、仲井さんにしろ。ストーリーとしては非常に深刻な話だったりするわけですが、ワンカット撮る毎にみんながゲラゲラ笑うような楽しい現場でした。映画からはたぶん、想像できないかもしれませんが、本当に楽しかったんです。
隈井士門さんと村田さんが演じた兄と妹の美しさも忘れ難いものがありますが、この映画以外はほとんど出ていないようですね?
そうですか。映画が映画ですからインパクトが強すぎて、他の作品には起用しにくくなるのかもしれません。別の映画に出ていた知り合いの女優さんも、その映画でのインパクトが強すぎて、仮に監督がその映画を評価していたとしても、なかなか声をかけてくれないと言っていましたね。仮に起用されても、その映画を超えることが出来ないのでは……という不安につきまとわれるので、監督も本人も怖くなるんじゃないですかね。
あのお二人にとっても大変なシーンはいくつかあったと思いますが、現場ではどんな様子でしたか?
そんなにしんどくはなかったんじゃないかな。彼女のほうはまだ10歳でしたからいろいろと理解できないことはあったんですが、偽ることなくきっちりと説明しました。
彼女のお顔とマネキンの顔はとても良く似ていましたね。佐野和宏さんが演じた役はお兄さんが成長した姿のように思えましたし。
そう思われましたか? それは嬉しいですね。そうなんですよ。これは実はスタッフにも現場で言っていなかったんですが、僕は輪廻をイメージしていました。少年時代に妹を愛して殺(あや)めてしまい、人間の女を愛せなくなり、青年期になってマネキンを愛し、そのマネキンも破滅的な運命を辿ります。その後、中年期のルンペンがいて、今度は木の股を愛してしまう。そして、チョイ役ですけど老人が出てきますね。こうしてつながっているので、僕としてもマネキンのカメラ・アングルは、少女の顔に似て見えるように工夫したつもりです。
差別だ、近親相姦だと騒ぎ立てますけど、差別なんて日常にあることですよね? それを映画で描くなというほうが不自然だと思いますが、なぜそれがタブーになってしまうんでしょう?
何なんでしょうね。僕はタブーなんてないと思いますけど。だって、例えば兄妹で愛し合ってしまったら、それは仕方ないでしょう? いろいろなリスクはつきまとうわけですが、それを覚悟した上だったら他人がとやかく言うことじゃないと思いますね。
お兄さんが愛する妹の臓物を食べるという行為も、観念的には理解し得ることですね。
ええ、彼は最も愛した存在の一部を、自分の中に埋葬したいだけなんですね。
この作品は中野武蔵野ホールの経営危機を救ったほどヒットしたということですが、どうしてそこまで観客に受け入れられたと思われましたか?
コンプレックスを持っている人間を徹底的に描きましたからね。おそらくは誰もがコンプレックスを持っているはずですから、映画館に来てまでそういうものを見たくないと思われる方は批判しますし、共感してくださる方はもう一回見たいと思ってくださいますし、ジャーナリストの方たちも含め、あちこちでこの映画の話をしてくださいますし、それが広がって、さまざまな分野の方たちが観に来てくださって、映画ファンだけにとどまらなかったということはあったかもしれません。テーマが普遍的だったのだと思います。それで、お客さんのコンプレックスの襞にちょっとでも引っかかってくれたのかな、と。
一番影響を受けた監督はどなたですか?
みんなですよ。どんなにつまらない映画でも好きなシーンがあったりするじゃないですか。見た以上は、詳しいことは忘れても、どこかに残っているものですよ。ただ、別格は黒澤 明さんと溝口 健二さんです。もちろん、小津安二郎さんも素晴らしいですし、海外にもいっぱいいます。フェリーニ、パゾリーニ、キューブリック、亡くなったばかりのベルイマンやアントニオーニとか。
亡くなった方も含め、一緒に仕事をしてみたい俳優を一人挙げるとしたら?
えっ!? なんで、そんなこと聞くの(笑)? ……今ふと頭に浮かんだのは、ジャン・ギャバン、マーロン・ブランド。
そうです。カラーなんです。
最後に、これから映画をご覧になる方々に向けて、メッセージをお願いいたします。
松井良彦です。9月1日、東京・渋谷のシアター・イメージフォーラムで『追悼のざわめき』が再上映されます。この映画を観ていただくと、人間の喜怒哀楽の感情のどれかひとつは必ず揺さぶられると思います。ぜひ、観にいらしてください。よろしくお願いいたします。
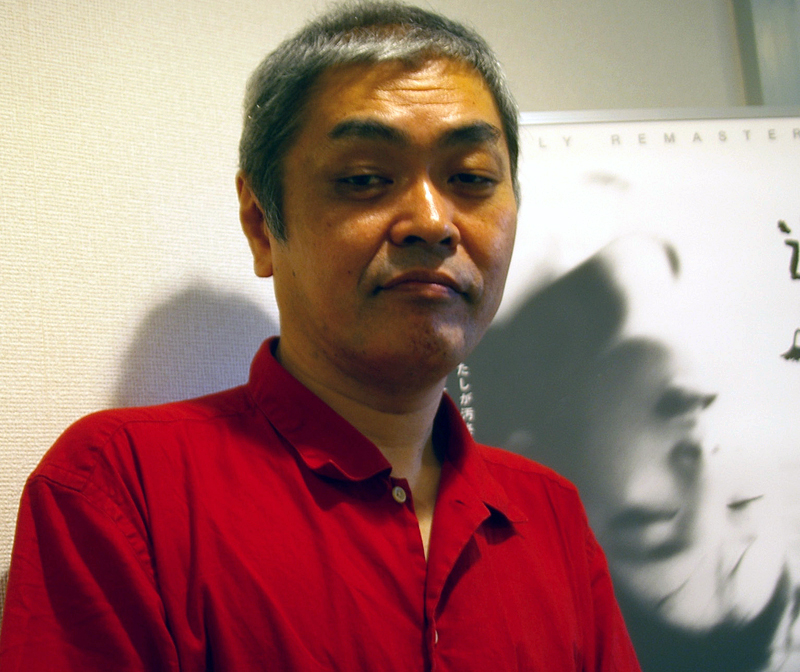

この映画を見るのは、ちょっとした覚悟が必要だった。見てしまったらトラウマとなって心に苦く残る映画というものがあり、もしかしたらその類の作品ではないかと思っていたので。でも、そこで私が見たのは、差別と嘲笑に満ちた憐みなき世界に荒々しくも息づく、異形にやつしたひたむきな愛の寓話だった。深い孤独に身をひたし、汚濁にまみれながら、深い愛を捧げる“もの”に触れる人々の姿はやがて清らかな光に包まれ、その残光は観る者の心に厳かに照射し、根源的な問いを投げかける。
監督がおっしゃるように、自身の中でどの種の感情が揺さぶられるのか、劇場で確かめてほしい。
(取材・文・写真:Maori Matsuura)
公開表記
配給:安岡フィルムズ、配給協力:バイオタイド
2007年9月1日(土)よりシアター・イメージフォーラムにてレイトショーほか全国順次公開







