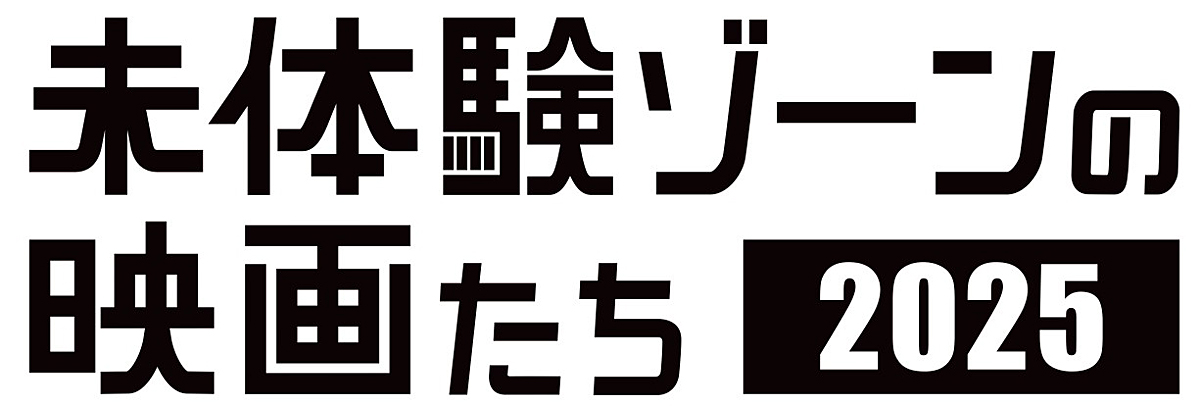7回目となる東京ドキュメンタリー映画祭が、2024年11月30日(土)〜12月13日(金)まで、新宿K’s cinemaにて開催される。
2019年『調査屋マオさんの恋文』で東京ドキュメンタリー映画祭のグランプリを受賞した今井いおり監督の最新作『今のほうが その続き』が長編部門にコンペにエントリーされている。映画の舞台は、大阪府吹田市。かつて学生寮だった古い建物「文福荘」を再生すべく、イベントを仕掛ける子育て世代の女性たちや、機織りを通じて出会った青年の新たなチャレンジを今井監督は独特の視点で捉えていく。「コミュニティの再生」と呼ぶにはちょっとフクザツな、一筋縄ではいかない展開に、今井監督はどう向き合ったのか。上映を前に話を聞いた。
今井いおり監督 プロフィール
1978年兵庫県淡路島生まれ。大阪在住。
2008年『安もんのバッタ』が中之島映画祭にてグランプリ。
2014年『ろまんちっくろーど~金木義男の優雅な人生~』劇場公開。
2019年『調査屋マオさんの恋文』が東京ドキュメンタリー映画祭グランプリ受賞。2020年に劇場公開。
この映画では、まず三原満里さんという熱量のある人が出てきて、かつて彼女が「文福荘」で教えていたミュージカル教室の教え子たちがおよそ20年ぶりに集い、コミュニティの再生みたいなことが描かれるのかと思いきや、意外な方向に話が飛躍していきます。そこで今井監督はあえてコミュニティの瓦解を描かないところが面白いと思いました。そもそも、このプロジェクトは何を撮りにいくところから始まったんですか。
もともと僕は、あの地域のケーブルテレビのディレクター15年以上やっていて、いわゆる街ブラでロケハンをしていた時にたまたま三原さんと出会って、最初はケーブルテレビで取材させていただいたんですよ。アトリエがあって、アーティストのための展示もやっています、みたいな話を番組で伝えました。
その後、大石さんという女性4人の中心人物から「私たち文福荘プロジェクトっていうのを始めるんですよ」と連絡が来たんで、じゃあ撮りましょうかと。ちょうど文福荘という、学生寮がボロボロやったから、何とかしてくれへん?と三原さんに言われて、大石さんたちが「私たちがやるわ」ということになった、という流れですね。
彼女たちは三原先生の教え子だったとのことですが、集まる感じが独特で、同窓会的ではあるにせよ、何で次々といろんなことをして盛り上がれるのだろうかと思いました。監督は取材をしていて、どうお感じになられました?
大石さんが、みんなを巻き込む力があるんです。大石さんの友人に大工さんがいたので大工のワークショップをやったり、「前田文化」という隣の茨木市を拠点に文化住宅とかでイベントをやるパフォーマンス集団を呼んだりとかして、とにかく盛り上げる力がすごい。
たまたまあの時期皆さんに、帰国や転職が重なって、奇跡的に時間ができたこともあると思うんですよ。東京で広告の仕事をしていた大石さんが辞めて時間があったり、別の方がアメリカへ行っていたんだけども、地元の吹田に戻ったりして。
吹田市というお土地柄もあるのでしょうか。あるいは、三原先生のパーソナリティによるところが大きいのでしょうか。
僕は最初、彼女たちは正直エリートに見えていました。あの地域は、ちょっと裕福な人たちが住むエリアでもあるんですよね。三原先生はそうじゃないっておっしゃっていますけどね。そこに三原先生に機織りを学び、文福壮で機織りを始めるうどん屋の岩見さんが絡んでくる面白さがあるんです。
岩見さんのうどん屋って、同じ吹田市でも、下町のエリアなんですよね。僕は岩見くんとしゃべっていて、あ、生きてきた世界が一緒だと思いました。吹田市は前の1970年万博の開催地でもありますが、1970年大阪万博の要素も若干分福プロジェクトにはあります。吹田は大阪では社長さんとか、そういう人が移り住んでくる町だから、比較的穏やかな人が多い印象です。
文福荘のオーナーである三原満里さん自身も、ただミュージカルの先生というだけじゃない。何かある種天性の企画者というか、オルガナイザーみたいなところがありますよね。
全てをポジティブに捉えている人で、明らかに失敗だと思えるようなことでも子どもたちに「良かったね」って言える人なんですよ。
元生徒たちが、自分の子どもを連れてきたりするんですけど、接し方がとんでもなく優しい。
こういう言葉がかけられる人だから、何十年経っても元生徒さんがついてくるんだろうなって。うちにも当時4歳ぐらいの娘がいましたから、あ、こういう言葉をかけたらいいんだなと、参考にさせていただきました(笑)。
同窓会的な雰囲気もありつつ、大人になって時間ができた時に、ああいうコミュニティーの作り方をすることの楽しさが、画面からすごく伝わってきました。
コミュニティということに関していうと、ちょうど僕も、その時子どもの小学校でPTAに入ったりして、当事者になったんですよね。当事者の視点で見たら、やっぱり彼女たちがやっていることって楽しいんですよね、この違いは何だろうと考えると、PTAのコミュニティは継続を目的にやっていたりするんですが、彼女たちは純粋に「面白いことには人が集まる」という文脈でやっている。僕からしたら、かつての教え子たちがおよそ20年ぶりに集まってか何かするってことだけで、もうロマンチックじゃないですか。その絆が本気で美しいなと思いましたし、僕もあの地域で長いことディレクターをやっていたんで、このシチュエーションを撮影できるのは自分へのご褒美かなと、傑作を手に入れたような思いで僕は撮っていました(笑)。
ところが映画は、文福荘のプロジェクトから、文福荘の中に放置されていた機織り機の復活や、機織り機を使って自分の店の暖簾を作る、うどん屋の岩見さんの話へとシフトしていきます。監督としては、どういう思いでこの変化をとらえていたのですか。
いろいろ事情があってゴールが変わっていっちゃうのは、ドキュメンタリーの難しいところですよね。文福荘の再生というよりは、そうじだけで終わってしまうような内容になるのはもったいないと思いながらも、前作『』調査屋マオさんの恋文』の公開時期でもあったので、とりあえず一旦置きました。
その後、コロナで僕の通常の仕事が全部飛んで暇になったので、文福荘の編集を改めて始めたら、やっぱり面白いんですよね。ここから何か作れるのかと悶々としているときに、文福荘で知り合ってから、ずっとつながっていた岩見くんのうどんを食べる機会があったんですね。
岩見くんも、コロナの時に、地元の小中学校の子どもたちにうどんをあげるイベントをするなどしていました。「ちょっと撮らせてくれへん?」って言った時に、うどん屋に本腰をいれる前の、人間として弱っていた時とはまるきり違う、目の輝きがあったんです。あ、これでいけるんじゃないかと思って。岩見くんが行動を起こして、のれんを作って自分を再生させていくっていう、再生というテーマで見せられるんじゃないかと思いました。自分の声のナレーションをしっかり入れて、自分が見た物語としてみせればね。
その時になぜ、「うどん屋の岩見さん」に着目したのですか。
僕に対して心の底から本音で話してくれたのが、彼だったんですよ。
機織りをしながら彼が僕にずっと語ってくれたことが心の声でした。僕も彼みたいなところもあって、20代後半までディレクターかバイトかみたいな感じでしたし、彼の悩みは、実は誰にでもあることなんじゃないかと思って。いま中学生になった僕の息子にも、この映画を何年か後に見せたら、「いつからでもやり直していいんだ、始めていいんだ」っていうメッセージを伝えられるかな、というのもありましたし。
それは具体的にいうと、岩見さんの、自分はうどん屋の息子なんだけど、このまま親の路線を継ぐだけでいいのかっていう葛藤ですよね。
そうです。理想と現実が一致しないことは誰しもあると思うけど、目標を見つけて、目の前のことを一生懸命やれば、自ずと道は開けていく、というね。彼の機織りをみてすごく感動したし、僕がPTAとかにストレスを感じていた時に、彼は地域のために何かしたいみたいなことを目を輝かせて言うんで、彼も大きな人になったなと実感しました。
文福荘のイベントを手がける人たちと、岩見さんが監督の中で繋がったのは、どの部分が一番大きかったんですかね。
そこはあんまり、偶然の出会いぐらいしかないと思うんですよね。共通点って何だろうと思った時に、これは時間の経過を描いた「時間の映画」だと思ったんですよ。仲良くさせていただいているミュージシャンの、よしこストンぺアさんの「ナキノ」って曲の中に「今のほうが、その続き」という歌詞があって、これを拠り所に作れないかなと思ったんです。
文福荘でわっと盛り上がるのは良いことなんだけど、物事は何でも表裏一体で、集まればまた別の感情が生まれてくる。そのようなことを体験したことがある人には、理解してくれるかなと思って。
時が経てば人生はそれぞれ違うフェーズに入り、変わるものもあれば、変わらぬものもある。その当たり前のことが、丁寧に撮られている感じがしました。監督ご自身は、こういう映画になったことに対して、どういう感想をお持ちですか。
機織りを始めて周りの人を集めたり、近所の人に応援してもらったりしている岩見くんをみていると、「幸せって何だろう」って思うことがあるんです。つきつめれば、良質な人間関係なんだと思います。良質な人間関係は、昔は多分お祭りでみこしを担ぐとか、地域が活性しながら作られていたのでしょうが、この映画では文福荘再生プロジェクトの盛り上がりとか、機織りとか、うどん屋さんののれん作りがきっかけになっている。うどん屋さんの岩見くんが、純粋に自分がやり直したいという思いでのれん作りをはじめたら、そこに人が集まって、人間関係ができていきますよね。文福荘の彼女たちも、一緒にやって人間関係ができて幸せになっていくのだなあと。
コミュニティを描く時に、ある種の壁や対立、人間同士の相克を描くのもドキュメンタリーだと思うのですが、本作は、対立よりも乗り越えていった人々の姿を描いている作品だったと思います。どうしてそういう方向の描き方をするのですか?
対立を描いてしまったら、この映画は成立しないだろうなと。人が集まればいいことも悪いこともあるけど、あえて撮影させていただいた人を傷つけてなくても、人間関係が続けていければ良いじゃないか、みたいな気持ちが根本的にあるんですよ。発信したいと思っていている人が目の前にいれば、対立を描かなくても、人間本音を聞き出せるし、映画としても見せられるものになる、というね。
表層の部分だけ描けば絵空事に見えてしまうけど、時の流れを経て、そこに留まらない人間の変化が映画に現れていると思いました。
時が経ち、人が成長する姿に本当に感動しました。過去に何かしら抱えている部分があり、それを手放すことで新たな道を見つけて歩き出してゆく。その姿は過去のしんどかった時期を思わせ、それを乗り越えた姿だと思います。また、三原先生と元生徒たちとの変わらない関係性は非常に魅力的だと思いました。これは三原先生のなせる技だと思います。時間が経つことで変わるもの、変わらないもの、それぞれが面白いと思います。
最後に、文福荘に放置されていた「機織り機」というのは、映画にとってはどういう存在だったと思いますか?
もちろん、機織り機の再生のために彼女たちは集まっているし、岩見さんは機織りを学ぼうとしてあそこに来ている。機織り機はそれらの人々を「紡ぐ存在」でしたから、機織り機が再び動き出すことがゴールだと思いながら映画を作っていました。僕もモノづくりはほんまに見ていて好きなんで、機織り機が動く様子を撮るのは、ただただ撮っていて楽しかったです。河原に草を撮りに行くシーンも入れましたが、そもそも糸ってあんなふうにできるって知らなかったですしね。
『今のほうが その続き』

(2024年、日本、上映時間:92分)
監督:今井いおり
大阪・吹田市にある元学生寮で、30年にわたり子どもたちに英会話やミュージカルを教えてきた女性。だが建物は老朽化し、趣味で買った機織り機が埋もれていた。そこにかつての教え子たちが集い、まちづくりの拠点として再生を試みる。やがて、現れたうどん屋の青年が機織りに興味を持ち……人と人、人と街、紡がれる思いの物語。
東京ドキュメンタリー映画祭2024
開催期間:11月30日(土)〜12月13日(金) 新宿K’s cinemaにて開催
【会場】新宿K’s cinema
【料金】一般 1600円 大・高1400円 シニア1200円
※ ご鑑賞の3日前0:00より上映時間の30分前まで劇場サイトよりチケットがご購入いただけます。
【特別鑑賞券発売中!】3回券 3,600円
※ 劇場窓口および映画祭事務局で販売
(映画祭期間中も販売しますが、売り切れ次第販売を終了します)
※ Web予約では使用できません 窓口にて指定席券とお引き換えください
●各回定員入れ替え制、全席指定
●上映開始後のご入場は、お断りさせていただく場合がございます。
●満席の場合は入場をお断りさせていただく場合がございます。
●作品により画像、音声が必ずしも良好でない場合がございます。あらかじめご了承下さい。
公式サイト
https://tdff-neoneo.com/(外部サイト)
公式X:https://twitter.com/TDFF_neoneo(外部サイト)
公式Facebook:https://www.facebook.com/tdff.neoneo(外部サイト)
(オフィシャル素材提供)