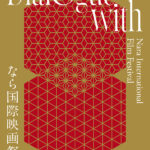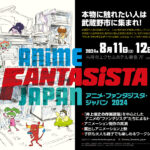「グローバル・アニメ・チャレンジ」(GAC)は才能ある若手アニメーター等が世界で通用する技術や制作姿勢、働き方を学び、世界でアニメ産業を牽引し指導者的な役割を担う人材になることを目指すプロジェクトで、独立行政法人日本芸術文化振興会に設置する基金を活用、かつ複数年度にわたって支援する事業の一つとなる。2024年7月31日にプロジェクト発表記者会見を開催し、11月15日(金)には11名のGAC候補生が発表。これまで各候補生との面談やSIGGRAPH Asiaの視察などが行われてきた。
2025年1月からは数土直志氏、ダグラス・モンゴメリー氏を招いた講義とワークショップが行われ、アニメーションを取り巻く世界や日本の状況についての議論が交わされた。そして、4月16日に第三回目のワークショップが開催され、アニメーターの井上俊之氏を招き講義とグループワークが行われた。
「グローバル・アニメ・チャレンジ」のプロジェクト概要および今後の活動内容ついては、公式サイトにてご確認いただける。
■公式サイト:https://global-anime-challenge.com/(外部サイト)
GAC 第三回ワークショップ概要
開催日:2025年4月16日(水)
場所:自律協生スタジオ(コンヴィヴィ)(武蔵美術大学 市ヶ谷キャンパス)
講師:井上俊之(アニメーター)
第三回目のワークショップの講師は、日本のアニメ業界をアニメーターとして牽引してきただけでなく、日本アニメーター・演出協会(JAniCA)の立ち上げに携わり、各メディアでも日本のアニメ業界の情報をアニメーターの目線で発信してきた井上俊之氏。現在はスタジオジブリの社員として活躍している井上氏へQ&A方式で講義が行われた。
第三回ワークショップ ポイント
●アニメ業界の労働環境は改善されているが、格差が生まれているのではないか。インターネットの発達により人材育成も進んでいる。経営者側がより整備していく必要はあるだろう。
●世界と日本のアニメの未来について。日本国内にだけ目を向け、同じようなルックになっていないか? キャラクターデザインやコンセプトワークの重要性について。世界に目を向け刺激を受けてほしい。
第三回ワークショップ報告
「業界をもう少し牽引していこうという気持ちでJAniCAの立ち上げに関わったこともあり、アニメ業界の正確な情報を一般の方にお伝えするためにアニメーターとして橋渡しができれば」という気持ちでラジオなどのメディア出演も行っているという井上氏。 この日は候補生の中目貴史さんを中心に質疑応答形式で講義が行われた。
現在のアニメ業界の労働環境について、「確実に良くなっていると思う」と話しつつ「格差が生まれているのではないか。条件が良い会社とそこに入れない人たち。能力や適正と会社の条件が必ずしもイコールでないのではないか」と指摘する井上氏。一方業界内でもよく取り沙汰される「働き手不足」問題についてや、優秀な人材の増やし方についても言及され、「優秀な人材は入ってきている印象。昔は優秀なクリエイターをチェックして名前を覚えることもできたが、この10年ほどは覚えることを放棄するくらい、筍のように人材が出てきていると思う。人手が足りないと言っているが、作品が多すぎるだけではないか。こんなにアニメーションの未来が明るく見える時代はなかったんじゃないか。今後、働き手不足の状況好転が望めるかどうかは、会社を経営する側のコントロールが必要」と語った。さらに人材教育については「昔は人材育成という発想がなかった。教えてもらったこともなければ教えたこともない。見て覚えるのが当たり前の世界で、見よう見まねでやるのが普通だった。今はインターネットの発達によってアニメのハウツーも学べるようになり、良い素材を繰り返し見ることができる。並行して各社もこのままじゃだめだよね、と現場で育てるという機運が醸成されてきた。さまざまな要素が重なっていると思うが、アニメーターにとって非常に良い環境だと思うし、素養のある人にとっては栄養になっているはず」と語った。
さらに、これからのアニメの未来について「いまはタイトル数も多く、レベルの高いスタジオも多い。だからこそキャラクターデザインのバリエーションを増やしていかないと。特に、海外からみるとジブリと湯浅政明作品、それ以外になってしまっているのではないか。ビジュアルの開発はかなり意識的に行っていくべき」と話し、「海外ではCGもだが、手描きアニメーションも増えている。ここ10年くらいで日本のアニメーションの影響を受けた人たちが一見すると日本のアニメかなと思うようなアニメを作っている。さまざまな問題を孕んではいるが、AIの技術も発達している。10年、20年後、世界でアニメを容易に作れるようになったときに世界での居場所がなくなってしまうかもしれない。危機感は持っていたほうがいいと思う」と警鐘を鳴らした。また、「かつて、アニメーターの技術だけでは弱いと思ったのか、一流画家を連れてきてビジュアル開発を行うことがあった。『呪術廻戦』ではカラースクリプトが役職としてクレジットされているが、昔のアニメ業界には概念的にもなかった役職。ピクサーなど海外のスタジオでは当たり前にあるもので発想として素晴らしいと思うし、今後は海外の真似をする、という必要性も出てくるのではないか」と話した。
講義の最後には井上氏から候補生へ「海外のアニメに興味を持っているか?」と質問が投げかけられた。「もっと(海外の作品に)感化されて欲しいし、アニメーションはもちろん、アニメーション以外の作品も見たほうがいいと思う。(今の日本の作品は)もし海外映画祭に出したら最初の10分で席をたたれてしまうような作品が多い気がする。イントロが面白くない作品は致命的。優秀な作品をとっかかりにして自分の作品にしてしまうようなことは大事だと思う。日本国内を見ているだけだと刺激がないと思うので、びっくりする体験をしてほしい」とメッセージを残した。
後半のグループワークでのディスカッションでは、井上氏による講義を振り返りながら、現在のアニメ業界の労働環境、雇用状況について、日本アニメのルック、コンセプトアートの必要性についての議論が交わされた。
近年アニメーターの正社員が増えており、社員としてアニメーターを増やしていきたいという会社は増加傾向にあるという。正社員雇用が積極的になされるようになったことでクリエイターの労働環境の改善は進んでいるようだが、やはり候補生からも「格差がある」と声が上がった。また、固定給がある会社を就職時の条件として選んだという候補生や、フリーで活動している候補生もおり、個人の考えや資質によって社員・フリーの選択がなされている部分が大きいという会話もなされた。
また、日本アニメのルック単一化の懸念についても議論が多く交わされ、「人気のデザイン(ルック)があるから、安定に走ることによって日本アニメへの間口が狭められているのでは」という会話から、「どこかの映画祭で上映された時に一目で日本製だと分かるのが日本のアニメーション。ジブリですら同じ範囲に入っているかもしれない。強みではあるけど、単一になっていくにつれ弱くなっていくという考え方はあると思う」という危機感についても話が広がった。井上氏の講義でも上がったコンセプトアートの必要性を感じている候補生は実際に多く、世界を見渡すと当たり前のように存在しているコンセプトアートが日本のアニメではあまり取り入れられていないという。「日本のアニメ制作システムは優秀で、そこには吸引力がある」「大きな会社であればあるほど重力が大きい」「キャラクターデザインで答えに辿り着こうとしていて、プリプロにかけるお金と時間の違いが(海外との違いとして)現れていると思う。ルックが似ているという問題にはさまざまな要因があると思うが、作り方が同じであること、そこに対して思考停止的になってしまっているのではないか」「そこから脱却したいと思っている」と積極的なディスカッションが行われた。
【講師プロフィール】
■井上俊之
1961年生まれ。アニメーター。『AKIRA』『魔女の宅急便』『人狼 JIN-ROH』『パプリカ』『電脳コイル』『おおかみこどもの雨と雪』『さよならの朝に約束の花をかざろう』など代表作多数。近年は『君たちはどう生きるか』や『ルックバック』などで活躍。現在はスタジオジブリ所属。第48回日本アカデミー賞では『ルックバック』原動画として「クリエイティブ貢献賞」を受賞した。著書に『井上俊之の作画遊蕩』(KADOKAWA、2024年)など。プとなった。
「グローバル・アニメ・チャレンジ」GAC候補生一覧
・伊藤優希(アニメーター)
・木村 誠(プロデューサー)
・工藤真奈(アニメーター)
・小出卓史(監督)
・斎藤圭一郎(監督)
・史耕(プロデューサー)
・篠原啓輔(監督)
・谷本 馨(アニメーター)
・中目貴史(プロデューサー)
・森山愛弓(演出家)
・山本ゆうすけ(監督)
「グローバル・アニメ・チャレンジ」について

■趣旨
日本アニメは今や世界中から注目を集めています。しかし、この業界を支える優秀な人材は日々の業務に追われており、グローバルな視点を養う機会は限られています。今後、日本アニメが国際市場で存在感を一層高めていくためには、現場の人材が国際的な経験や視点、感覚を身につけることが不可欠です。
こうした問題意識から、我々は「グローバル・アニメ・チャレンジ」を企画しました。これは3年間をかけて世界で活躍できる次世代クリエイターを育成しようという試みです。国内から才能ある若手アニメーター、プロデューサー、演出家/監督の計6名を選び出し、文化芸術活動基盤強化基金を活用して、英語のマンツーマン特訓と海外展開に関するワークショップ、海外の一流スタジオでのインターンシップ、パイロットフィルムの制作と海外アニメイベントへの出展を経験してもらいます。
この挑戦を経て得られた新たな発見や創作姿勢を土台に、彼らが将来、アニメ業界に革新をもたらすリーダーに成長することが我々の願いです。
■指導者
数土直志、菊池 剛、櫻井大樹、植田益朗
■スケジュール
2024年11月:育成対象者決定・発表
2025年1月:育成対象者への国内でのワークショップ(月1回程度)およびマンツーマンの英語特訓(週1回程度)開始
2025年夏頃〜:海外アニメ制作スタジオへの派遣(3ヵ月)
2025年〜2026年夏頃:パイロットフィルム制作
2026年6~10月:アヌシー国際アニメーション映画祭(仏)やアニメエキスポ(米)に出展
■事業主体
株式会社キネマシトラス
キネマシトラスは「100年残る、時代が変わっても変わらない価値観が入っているフィルムを産み出す」を理念に、2008年に設立したアニメーション企画・制作を行う会社です。
■パートナー
株式会社日本総合研究所
日本総合研究所は、シンクタンク・コンサルティング・ITソリューションの3つの機能を有する総合情報サービス企業です。「新たな顧客価値の共創」を基本理念とし、課題の発見、問題解決のための具体的な提案およびその実行支援を行なっています。
■協力企業・協力者
株式会社プロダクション・アイジー
株式会社オー・エル・エム
株式会社バンダイナムコフィルムワークス
宇佐義大(株式会社トリガー)
舛本和也(株式会社トリガー)
■公式サイト:https://global-anime-challenge.com/(外部サイト)
助成:文化芸術活動基盤強化基金(クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業)| 独立行政法人日本芸術文化振興会
(オフィシャル素材提供)