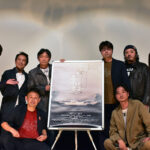渋谷のナイトクラブで働く現代の若者が死んだ兄の恋人と出会い、純粋な恋心に沈んでゆくさまを、衝動と静けさとと生々しさをもって<深淵を>描く純愛物語『ABYSS アビス』。
9月16日(土)には都内劇場にて公開記念舞台挨拶が行われ、監督・主演の須藤 蓮、共同脚本の渡辺あやが登壇した。
公開を迎えて、須藤はまず「昨日が初日で舞台挨拶だったのですが、企画を準備しはじめてから4~5年経っていて、編集だけでも1年半~2年かけた作品なので、噛みすぎたガムみたいになんの味もしなかったどうしようと思いながらお客様の前に立ったのですが、わっと込み上げるものがきました。あきるほど時間をかけて作った映画を観てもらうことで特別な気分になる映画はすばらしいものだと再確認しました」と挨拶。

その姿を横でみていた渡辺は、「目から涙を出しているので、コンタクトがズレたみたいで?とお客さまにも言ってしまったんですが、感動してたみたいで(ここで)訂正できてよかったです」。
渡辺の脚本で須藤の監督デビュー作品『逆光』に続いてのタッグだが、本作の企画が先だったということについて須藤は「元々この作品は、監督作としてというより、自分が出る作品を自分で準備した作品なんです。コロナ前に、その脚本を渡辺あやさんにを書いていただきたいという思いでアプローチをしました」。その補足として渡辺は「いざ脚本ができて、『これ誰が撮るの?』と聞くと、『監督考えてないです。あやさん撮ります?』と。『私は撮らないよ、君が撮れば?』というと『俺が撮ります』となりました。その段階では、彼の映画監督としての才能は、正直まったく見当もついてなかったんです。ただ、やりたいならやればいいのではと思って、『失敗しても自分たちでお金を出して作るものだし、ダメ元でやればいいんじゃない』としか実は思ってなかった。だけど、彼の中にずっとものを作りたいという、強烈な表現欲が眠っていながら、自分はそれに値しない人間だという強い思い込みの中に閉じ込めてたんだと思うんです。それが、徐々に現れ出したというのが、今日にいたるまで見ていて感じる過程です」。

NHKドラマ「ワンダーウォール」で出会ってからの縁というふたりについて、須藤は「京都の古い学生寮を舞台にしたドラマの脚本かとメインキャストの一人として出会いました。その劇場版をこのシネクイントさんで上映していただき、緊急事態宣言あけの頃に舞台挨拶に立ちました。お客さまもしんどい状況だったので、それを思うと今日こんなにたくさんのお客さまに迎えてもらってとてもうれしいです」。

渡辺は「ある日突然、たぶん携帯で書いたんだろうなと思うような脚本の切れっ端が送られてきて“脚本書いたので読んで下さい”と言われたのですが、“忙しいから”とすぐに突っ返したんです。若い方で映画を撮りたいという方が脚本を送ってくださったりするのですが、それに対して私は脚本家としてハードル下げないことを心がけてるんです。プロとして示せる、チキンと守るということは容赦しない。彼にも当然そのように接したら、普通は皆1回で心折れて去っていってしまうんです。彼は何回も何回も書き直して送りつけてくるんです。それで、それにつきあっていくうちにひとつの脚本になっていくわけです。それだけではなく、彼が書いたものに魅力を感じたひとつは、体験や出てくる人たちが、彼自身の生々しいものを書き起こしていると脚本の段階で感じられたことなんです。私には書けないものなので、たいへん魅力的でした。暴力をふるわれてる先輩からなぜ逃げないのかなど、人間関係の矛盾みたいなものは当事者しか分からないところがあると思うんです。それは面白いものになるのではと」。

「役者をやったり表現にたずさわりながら、手先やちょっとした考えから起きてくるものではなく、全身の中にある汚いもの綺麗なものふくめて、いままでの経験などを思い切りぶつけられる場所って実はそう多くなく、すごく求めていたました。小説の気迫のような、手触りのあることに関わりたくて、実体験を全部使いきってやるような気持ちで挑みました」と須藤。
渡辺は「前作とちがい、渋谷の街中で、しかも主演もして無茶でしかない撮影ではあったんですよね。1年後に撮り直したり、追加撮影をしてました」。そのひとつである水中シーンは「映画の素人なので、夜の海や水の中で撮影する、などやってないけないことをどんどん好きにやりました。水中シーンは都会かけぬけて田舎にいって解放され、どこにたどりつくのか。それを描くのに、人間が感じてることをどうやって映像にするのか、現実の描写だけだと想像するだけにとどまるので限界がある。はっきりと非現実を撮ってみせることでしかできないこともあるなと思ったので、水中撮影がとれてよかったです。喫煙所のシーンも全部撮影し直しました」。
そんな須藤 蓮というエネルギー体について、渡辺は「大きい種みたいなものを渡され、何になるか分からないけど埋めて水をかけずにはいられない、とはじめて会った時に感じました。でかいし、すごいものがなりそうという期待感とともに伸びていくのを見てるという感じです。いまも途中なので、まだ正直何になるかも分からないです。怖さもあるというか、でかく太く伸びてるなという実感はある感じですね」と捉える。「この間、「誰か代わってくれないかな」と言ってましたよ。たいへんすぎて、と(笑)」と須藤が返す。「僕自身もまったく分からないです。いまは素敵な大人たちがサポートしてくれるので『ABYSS アビス』を作ってる時よりは、自分が何をしたいか分かってきたんですが、まだ分かってないです」。
渡辺は「映画業界で20年ほど仕事をして、新しい動きみたいなのが業界の中に欲しいなと思っていて。長く続けてきた私たちの固定概念からなかなか自由になれない世代には無理なことで(須藤のような)、こういう何がしたいか分からない人に、何か分からないけどやってもらうしかないという期待を込めて、誰かに代わって欲しいけど、横から見てたいなと思っております」。
製作、脚本、監督、主演と大変なリスクを全部背負って生み出すことについて須藤は「若者特有のアクというのが邪魔をする」という編集の大変さを語り、「この作品が教えてくれたのは、がんばるということは大した勝ちはないということ。楽しみ出してから、面白いと思いだしてから作品がようやく形になっていきました」。
その後、はじめての監督としてのオーディションやキャスティングの面白さやについて盛り上がると、次の目指すことについて、最近訪れた台湾ではじめて海外にでた経験から「どうやって進むか分からない冒険が好き。海外でなにかやりたいと決めていますね。先が見えると興奮できないけど、何が起こるかか分からないことで自分の力を発揮できる、自我から解放してくれる、と思ってます」と期待を込めていた。
最後に、「小さな作品ではありますが、普段の仕事ではできないことができたという実感があります。機会があればこういった作品にを作り続けていきたいし、作られていくことを願いたいと思います」と渡辺が締めくくると、須藤は「真剣になり続けられるって、実は貴重なことだと最近思ってます。映画以外の世界でも、自分が面白いと思えるものを探して、突き進んでいきたいと思ってるのですが、初日を経てやっぱり映画いいな、と思いました。賛否はあっても結実させた作品の塊みたいなものがお客様に届くという尊さをあらためて感じました。自分の魂のようなものをお客様にお渡しできたことが本当にうれしいです。今日は本当にありがとうございました」と観客に感謝を述べた。
登壇者: 須藤 蓮監督、渡辺あや(共同脚本)
MC:伊藤さとり
公開表記
配給:FOL
2023年9月15日より渋谷シネクイントほか全国ロードショー
(オフィシャル素材提供)